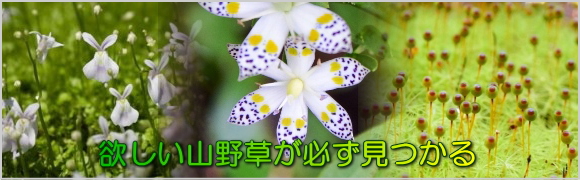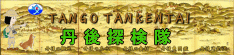I'll enjoy gardening by making by hand.
タムシバ(田虫葉) モクレン科 モクレン属
早春の花木
山地に生える落葉小高木で、早春に芳香のある白い6弁の花を葉に先立って咲かせます。
コブシの花に非常によく似ますが、コブシは花の直ぐ裏に葉を一枚付けるのに対し、タムシバは葉がありません。
葉は互生し長楕円形でよく似たコブシよりも細長いです。またタムシバの葉裏は白味を帯びています。果実は袋果が集まった集合果を付けます。
タムシバは高木型と低木型があり、西日本に分布するのは高木型で、東日本に分布する低木型とは雄蕊・雌蕊の数が大きく違うので、この二つの型は別種と考えられています。
タムシバの名の由来は、葉や枝を噛むと独特の甘みがあり、山作業の合間に噛まれたことから、(噛む柴)が転じてタムシバになったとされます。
また、花や枝に芳香があることから、別名をニオイコブシとも言い、ここ丹後の「安寿と厨子王」の悲話が残る建部山の麓では、タムシバを安寿姫の化身として「ニオイコブシ」と親しみを込めて呼んでいます。
「安寿姫の化身 ニオイコブシの咲く建部山に登る」は←こちらから

欲しい山野草は?